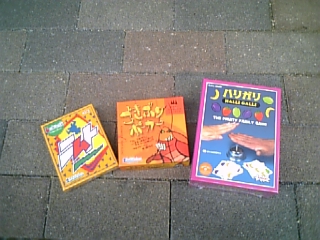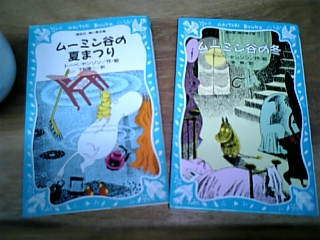その9 晴れでも雨でも楽しめる「お天気ハウス」
 エルツ山地の工芸品で私のお気に入りの一つ、「お天気ハウス」。かわいいお家の玄関に、男の人と女の人が立っています。晴れた日には男の人、雨の日には女の人が、玄関先に出てきます。
エルツ山地の工芸品で私のお気に入りの一つ、「お天気ハウス」。かわいいお家の玄関に、男の人と女の人が立っています。晴れた日には男の人、雨の日には女の人が、玄関先に出てきます。
馬の尾の伸縮を利用してつくられたもので、「簡易湿度計」みたいなもの。でもなぜ、女の人が「雨の日」に出てくる???湿度が高いと確かに不快な気分になりますが、それは男女一緒のはずなのに。
ザイフェンで作られているキャンドルスタンドに、「天使と鉱夫」というものがあります。
昔、鉱山で働く夫を無事に帰宅することを願いながら、妻は窓辺に置いたロウソク台に灯りをともしました。疲れた体を引きずりながら真っ暗な夜道を歩く夫は、我が家の窓辺に灯りがともっているのを見て、安堵する。敬謙な信者だった夫は、妻のことを真っ暗な鉱道の中で一日働く自分たちを明るく導いてくれる「天使」のような存在だと考え、キャンドルスタンドを作りました。その後、自分をモデルにした「鉱夫」の人形を横に並べられるようになりました。
「お天気ハウス」において、天使のような妻は、夫を晴の舞台に立たせるために、あえて、ジメジメした湿度の高い雨の日に自分が表に出ることを選んだのではと、私は考えます。
残念ながら「お天気ハウス」については、エルツ山地の工芸品について書かれた本を見ても、ネットで検索しても資料はあまりみあたらず、これが作られるようになったいきさつはよくわかりません。もし詳しい方がこのメルマガを読まれたら、ぜひご一報ください。
ちなみに、くるみ割り人形の父と呼ばれているWilhelm Friedrich Fuechtner(1844〜1923年)は「天使と鉱夫」のキャンドルスタンドの基礎となるものを最初に作った職人でもあります。
□キャンドルスタンド
http://www.hyakuchomori.co.jp/life/kogei/candle_stand/index.html
□フュヒトナー家のくるみ割り人形
http://www.hyakuchomori.co.jp/life/kogei/fuechtner/fuechtner_top.shtml